
京都医療科学大学は、日本で最も長い歴史を持つ「診療放射線技師養成」の単科大学です。
長年にわたり、診療放射線技師の育成に携わってきた本学だからこそ、「診療放射線技師とは何か?」「放射線を学ぶことにどんな価値があるのか?」といった疑問にお答えすることができます!
この連載では、京都医療科学大学の個性豊かな教員に、放射線の仕組みや診療放射線技師の魅力、この大学で学ぶ意義などについて聞いていきたいと思います。
Vol.1前編では、放射線技術科の霜村 康平(しもむら こうへい)講師が担当します。
診療放射線技師としての豊富な経験を持ち、放射線治療技術の基礎研究などに取り組む霜村先生に、放射線や放射線治療の仕組み、この分野の将来性などについて詳しく聞いてみましょう。
【霜村 康平(しもむら こうへい):診療放射線技師、放射線治療専門放射線技師、医学物理士】
京都医療科学大学を卒業し、名古屋大学に編入。卒業後、医療機関で診療放射線技師として11年従事したあと、2018年に京都医療科学大学の教員に着任。専門分野は、放射線治療、放射線計測など。担当する、放射線治療技術学、診療放射線技術学概論などの科目では、診療放射線技師、研究員としての経験を活かした、「実践的な生きた知識が楽しく学べる授業」を実践。学生たちに診療放射線技師の魅力や意義を伝えている。
もくじ
「物体を通り抜ける」放射線の不思議な力
放射線って危険?それとも便利?知っておきたい基礎知識
――霜村先生突然ですが、「放射線」について知りたいのですが、「放射線」ってそもそも何ですか?
確かに放射線という言葉はよく耳にするものの、その仕組みや働きはあまり知られていないかもしれませんね。
放射線って聞くと、ちょっと怖いイメージをお持ちの方が多いかと。でも実は、私たちの身近なところにも存在していて、医療や科学の世界で大活躍しているんです!
光や紫外線、赤外線などの私たちの身近にあるものも放射線に分類されるのですが、その内、高いエネルギーを持ち、物体を電離する能力を持つものを、一般的に「放射線」と呼んでいます。
――光や紫外線も放射線の一種なのは意外でした!放射線と聞くと、怖いイメージがありますが身近なものだったんですね!ちなみに、「被ばく」とはどういうことですか?
「被ばく」というのは、放射線を体に浴びることを意味します。紫外線や自然放射線によって、私たちは日常生活でも少しずつ放射線を浴びています。
放射線は、細胞のDNAを切断する能力を持っていますが、少量の放射線であれば切断されたDNAが修復されるため、健康を害することはありません。危険なのは「一度に大量の放射線を浴びる」ことで、DNAの修復が追いつかないことで、身体にさまざまな悪影響を及ぼします。

――では、医療で使う放射線は安全なんですね?
医療分野では、放射線の被ばくによって受けるリスクより、得られるメリットが大きい場合に、X線検査やCT検査、放射線治療などで、広く安全に利用されています。
医療で使われる放射線
レントゲンの仕組み・診療放射線技師を知る
――ずばりレントゲン写真の仕組みが知りたいです。
放射線は「物体を通り抜ける(透過)」とお話しましたが、実は透過しやすいものと透過しにくいものがあります。人体では、密度が高い骨は透過しにくく、肺はそれに比べて透過しやすいものとなります。
X線写真は、黒い影の中に骨が白く浮かび上がって見えますよね?これは、「X線が透過しやすい場所(肺)は黒く、X線が透過しにくい骨などは白く写る」というシンプルな仕組みによるものです。
X線撮影とは、人体を通り抜けたX線の量を測り、内部の構造や異常を映し出す特殊な画像を作ることなんです。
――意外にシンプルなんですね!レントゲン写真を撮影してくれた人が診療放射線技師さんなんですよね?
その通りです。診療放射線技師は、病院や検診などで、医師や歯科医師の指示のもと、放射線を用いた検査や治療を行う医療技術職(国家資格)です。外からは見えない体の内部の構造や異常を映し出すことで、現代医療を支える「画像診断」の世界で、たくさんの診療放射線技師が活躍しています。
「細胞を破壊する」のに“がん”が治る?
放射線治療の仕組みと発展
――放射線の性質や医療に活用されている理由が少しずつ理解できてきました!治療にも放射線が使われると聞きましたが、これはどのような仕組みなのでしょう?
「一度に大量の放射線を浴びるとたくさんのDNAが破壊される」という働きを活かしているのが放射線によるがん治療です。がん細胞に集中的にX線を照射(当てる)し、DNAを破壊するのが基本的な仕組みです。
――身体へのダメージや副作用はないのでしょうか?また、ダメージや副作用を避けるための工夫などはあるのですか?
一度に大量の放射線を照射すると、正常な細胞も同様にダメージを受けてしまいます。そのため、数週間から1か月ほどかけて、正常な細胞を可能な限り避け、分割しながら、毎日照射して治療するのが一般的です。
そうすることで、正常な細胞への影響を抑えながらがんを治療することができます。とはいえ、影響をゼロにすることはできないため、「可能な限り副作用を抑えた治療」のために、診療放射線技師が携わっているのです。

――なるほど。そこが診療放射線技師の腕の見せ所なんですね!
最良の放射線治療を提供するには、がんの位置と範囲を正確に見極め、適切な照射範囲と放射線の量を調整する技術と経験が必要です。
このようなプロセス全体を技術的にコントロールし、医師をサポートするのが放射線技術の専門家である診療放射線技師の役割であり存在意義なのです。

治療期間の短縮と治療精度の向上を実現!
技術革新とAIで実現する最先端放射線治療の世界
――放射線治療のトレンドについて教えてください。
まずは、放射線を発生させて照射する医療機器の進化があげられます。
以前は、一定量の放射線を、均等に照射することしかできなかったのですが、技術の進化によって、「ある部分は多く、ある部分は少なく」、放射線の量を細かく調整できるようになりました。この技術によって、複雑かつスピーディーな照射が可能になり、副作用を抑えたがん治療を安全に実施できるようになったと思います。
さらに、放射線治療はミリ単位で照射範囲を決めるのですが、呼吸などによってがんの位置が移動、または形状が変化し、照射する位置や範囲が治療時に変わることがあります。
このようなズレは、副作用の増大や治療の成績低下につながるのですが、がんの位置や大きさを治療時に取得でき、適切に照射できる技術が開発されたことで、大幅に改善されました。ただし、がんの位置や大きさは人の目で最後は確認が必要となり、診療放射線技師が担っています。
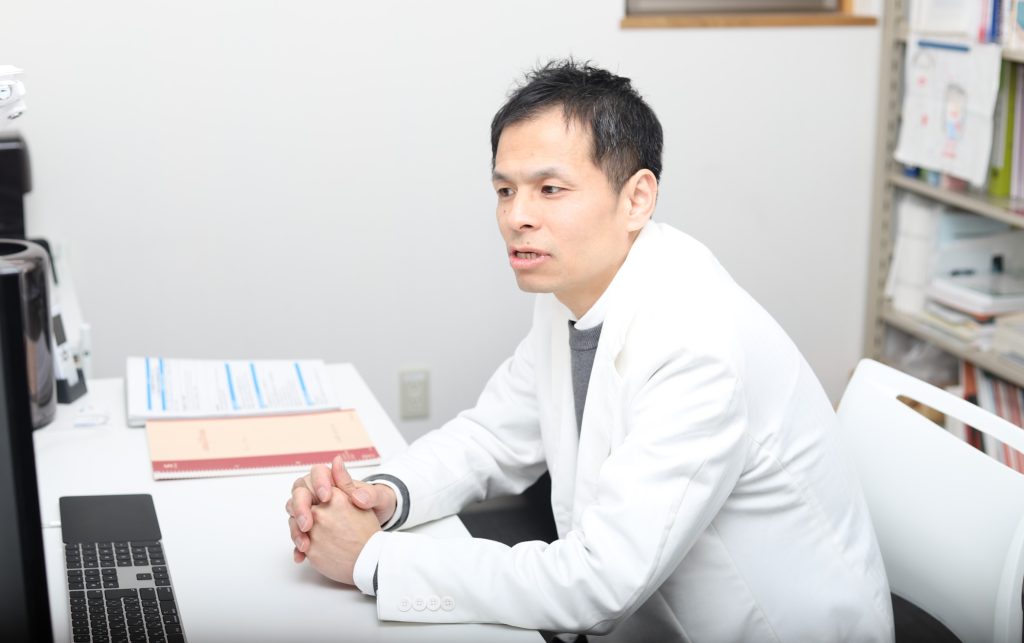
――他業界では、DXやAIなど、最先端テクノロジーが業務効率化や生産性向上に活かされていますが、放射線治療の分野でも最先端テクノロジーは使われているのでしょうか?
もちろんです。特にAIの導入は大きなインパクトがありました。
放射線治療は、作業工程が非常に複雑で、治療決定から開始まで時間がかかります。AIにこれまでの膨大な治療データを学習させることで、時間のかかる工程の一部をAIに任せられるようになり、準備期間を短縮できるようになりました。
もちろん、診療放射線技師によるチェックや修正は不可欠ですが、AIの導入によって、放射線治療の効果や安全性が進歩したといえるでしょう。
――医療機器の進化やAIの導入は、患者さん目線で見ると、どのようなメリットがあるのでしょう?
「ダメージを抑えながら、短期間で効果的な治療が行える」という点だと思います。たとえば、乳がんや前立腺がんの放射線治療は2か月程度かかるのが一般的でしたが、わずか2~3週間で完了する症例も出てきています。
働き盛りの方ががんに罹った場合、長期間の休職、または退職が必要なケースもありましたが、治療期間が短くなったことで、経済活動への影響が大幅に軽減でき、QOL(Quality of life)の向上に大きな役割を果たしています。
精度の向上により、がんが治りやすくなったというのはもちろんですが、「日常生活を維持しながら治療が行える」という点も患者さんたちに安心感を与えていると感じますね。
測定技術の発展と最新医療機器の普及を目指して
霜村先生が考える現代放射線治療の課題とは?
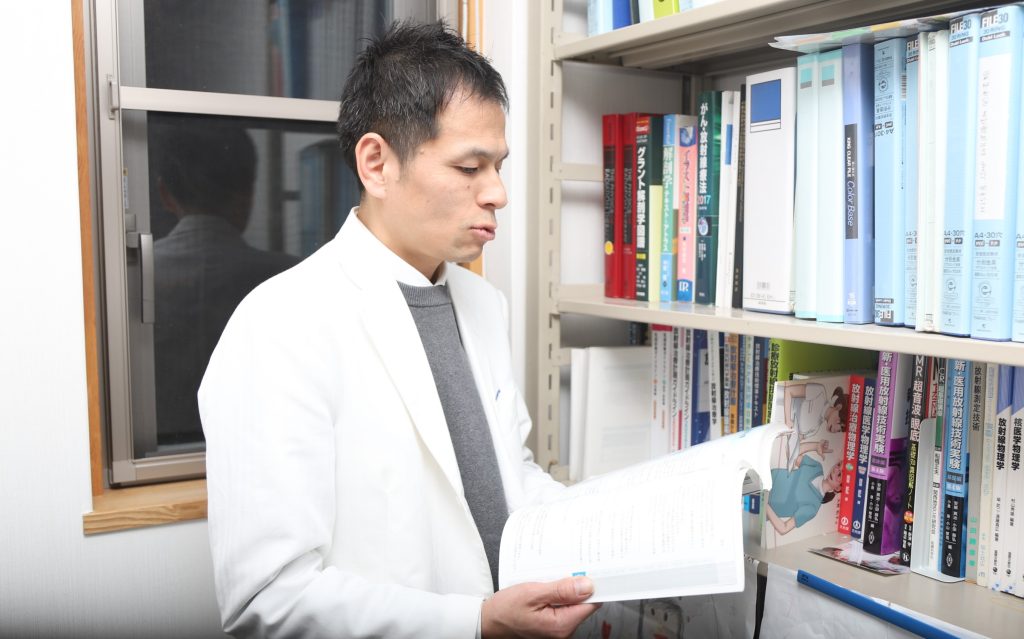
――技術の進化によって、あらゆる面で精度が向上し、より安全で効率的に放射線治療を受けられるようになっているのですね!放射線治療は非常に効果的な治療方法だと感じたのですが、逆に課題となっている部分などはあるのでしょうか?
課題はまだまだたくさん残されています。
私が研究を通して関わる分野は大きく分けて二つあり、その一つは放射線量の測定技術です。放射線治療では放射線の量は、薬の量と同じです。一般的に、薬は目で分量を計測できますが、放射線量は目に見えないため、高度な測定技術が必要となります。そのため、安定した精度の向上を目指すための技術開発が現在も進められています。
もうひとつは、国内における放射線治療の普及向上に関わる調査です。諸外国と比べ、日本は高精度な放射線治療の普及が十分に進んでいない現状があります。そのため、「技術革新の恩恵を全国の患者さんたちに届けられていない」という課題があります。より多くの医療機関で高精度な放射線治療が受けられるように、診療放射線技師の育成や医療体制の整備が必要だと考えています。
医療技術の発展によって、より多くの命を救えるようになりましたが、がん治療の改善におそらく終わりはありません。
私が専門で取り組んでいるのはこれらの2つの分野ですが、本大学はもちろん、世界中の研究者や診療放射線技師が、がんによって失われる命を少しでも減らすために日夜努力を続けています。
――霜村先生ありがとうございます。前編では、放射線の働きや仕組みから、放射線治療の現状・課題まで、先生たちが向かい合う「放射線治療の世界」の一端に触れることができました!後編では、少しだけ触れていただいた先生の研究テーマのほか、京都医療科学大学で学ぶことの魅力などについて深掘りしていきます。引き続きよろしくお願いいたします!
